Brand New Days4 星に願いを
登録日:24年06月30日


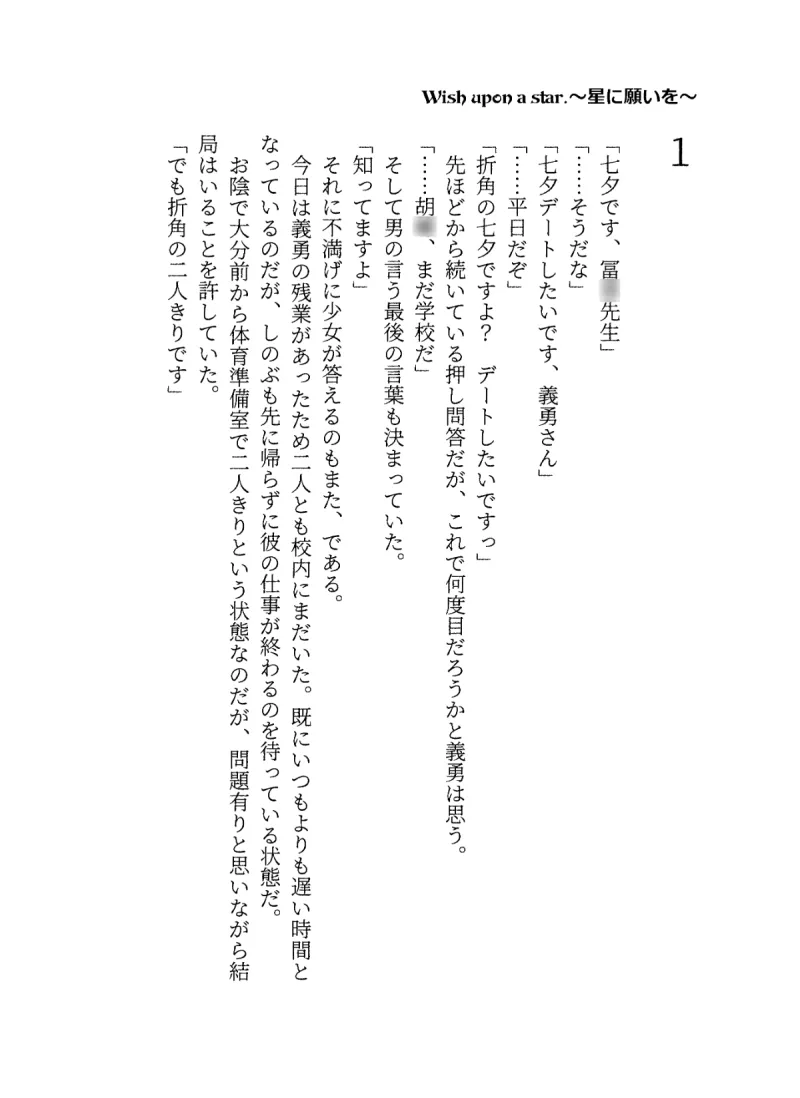
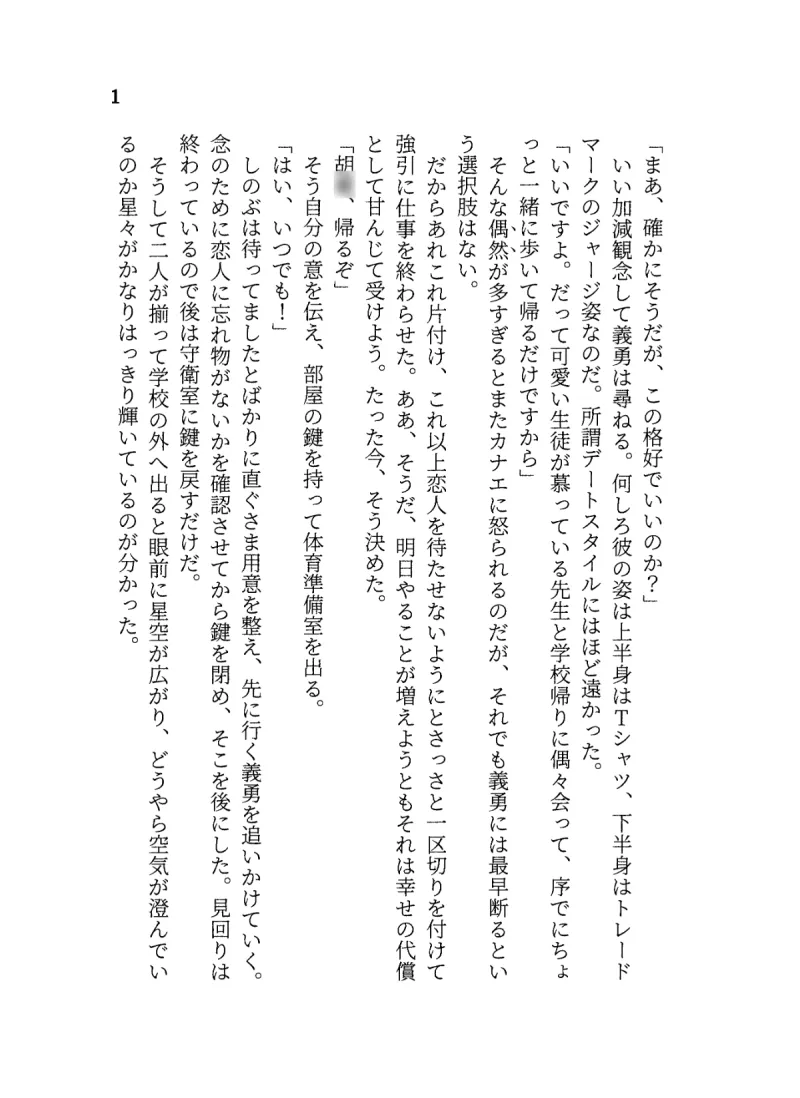
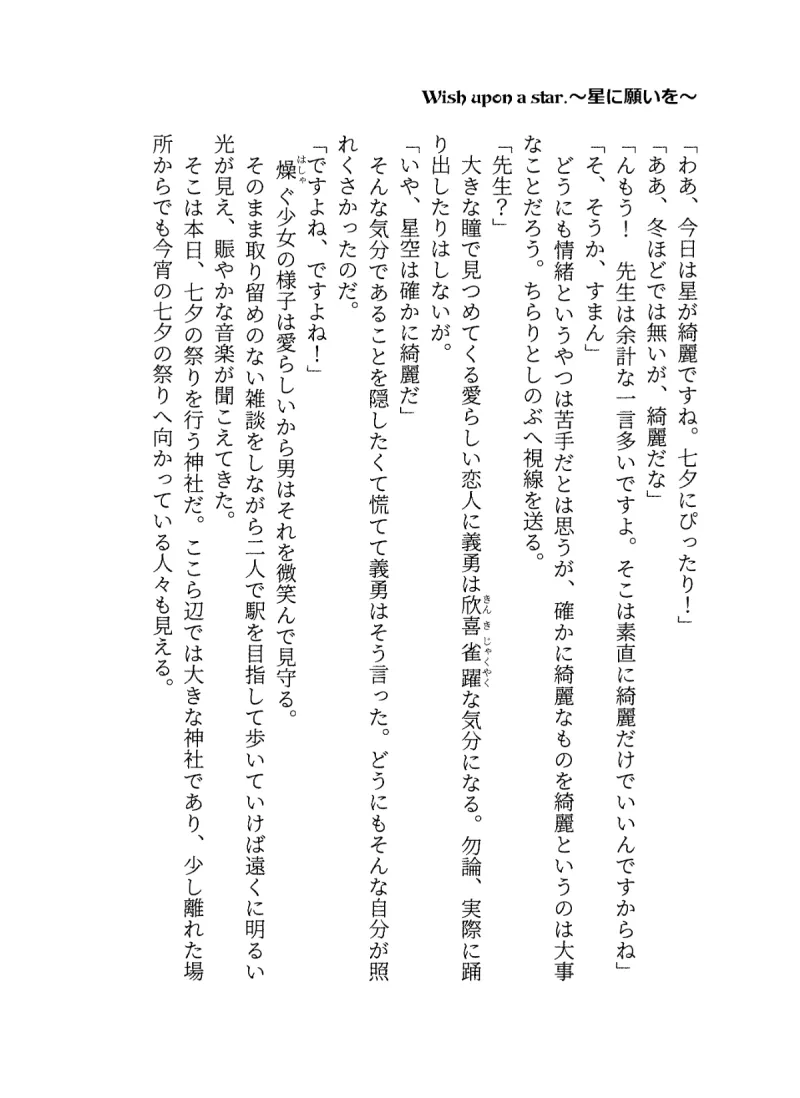
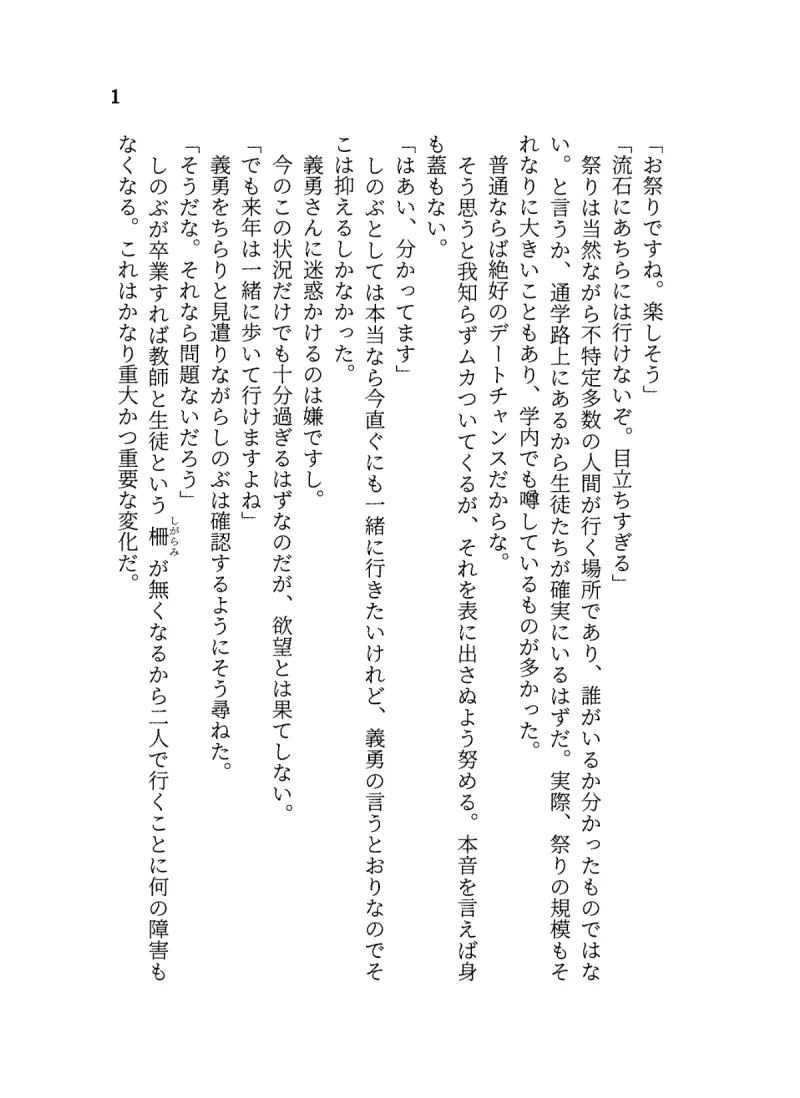
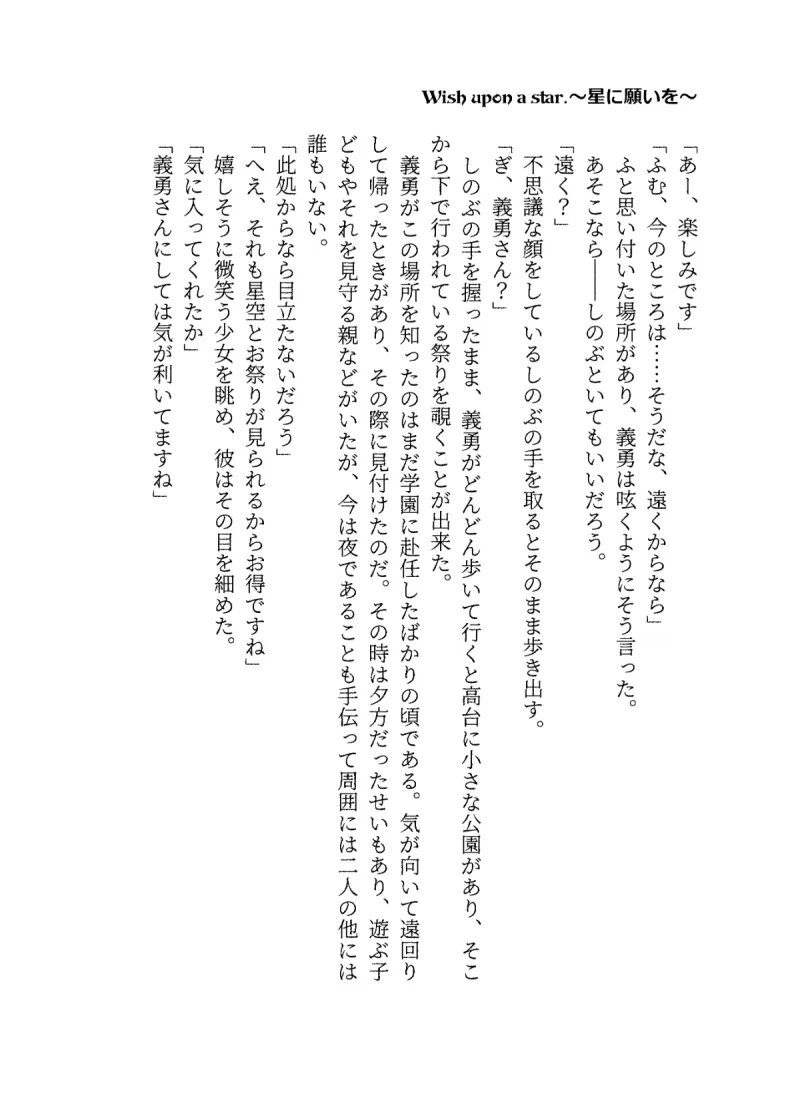
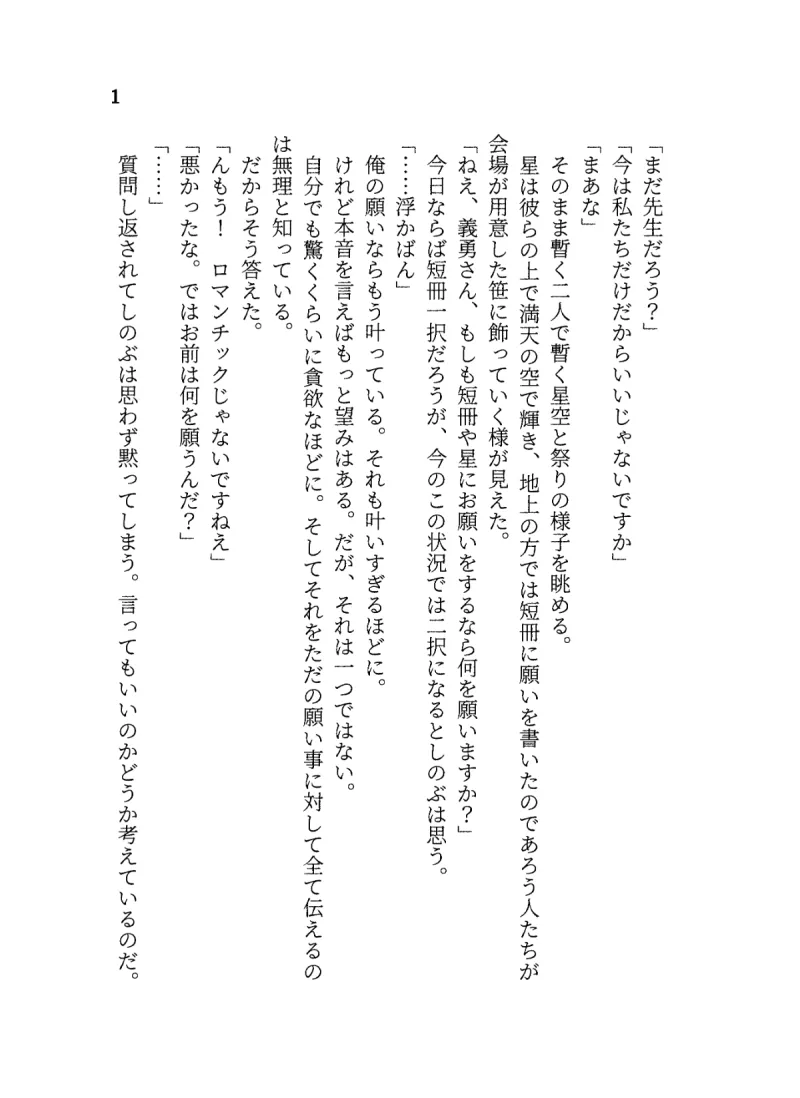
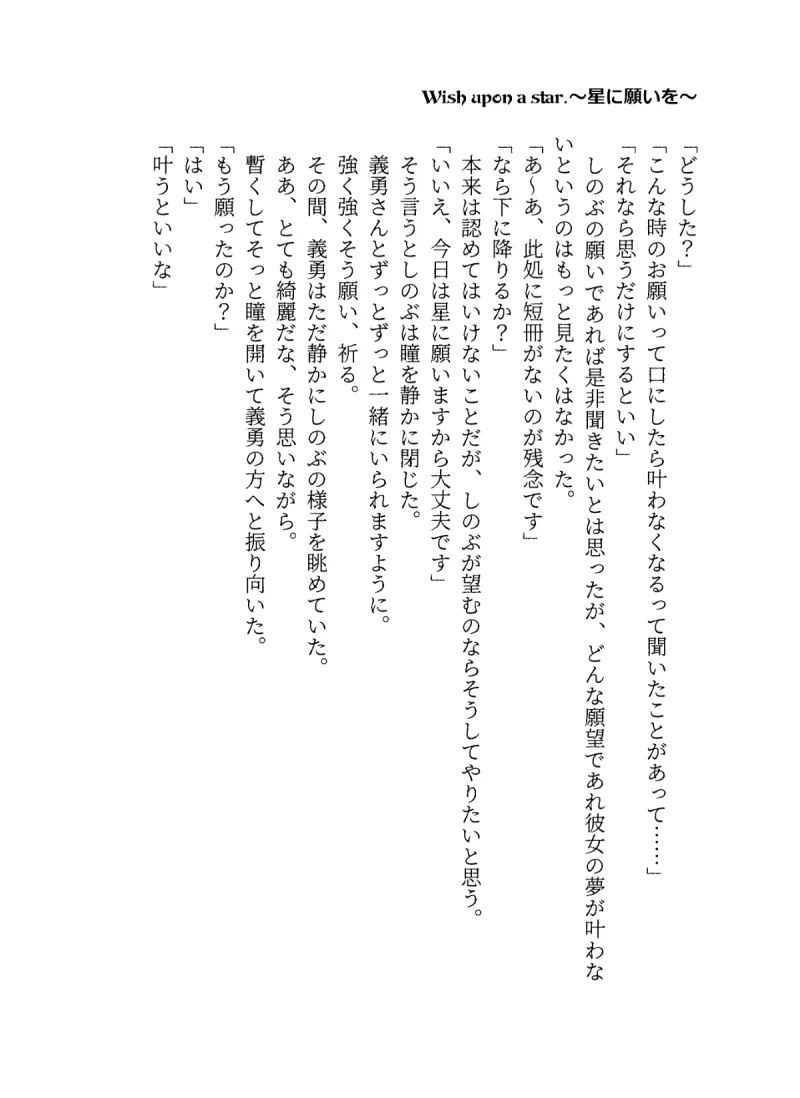
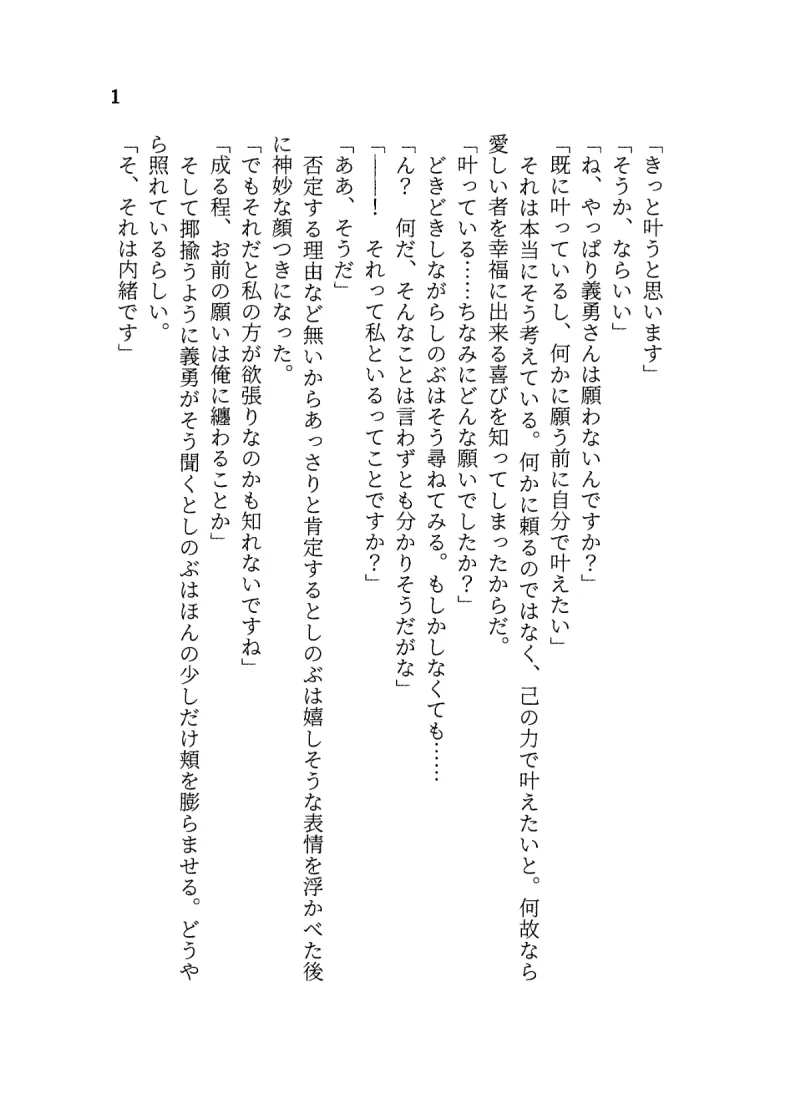
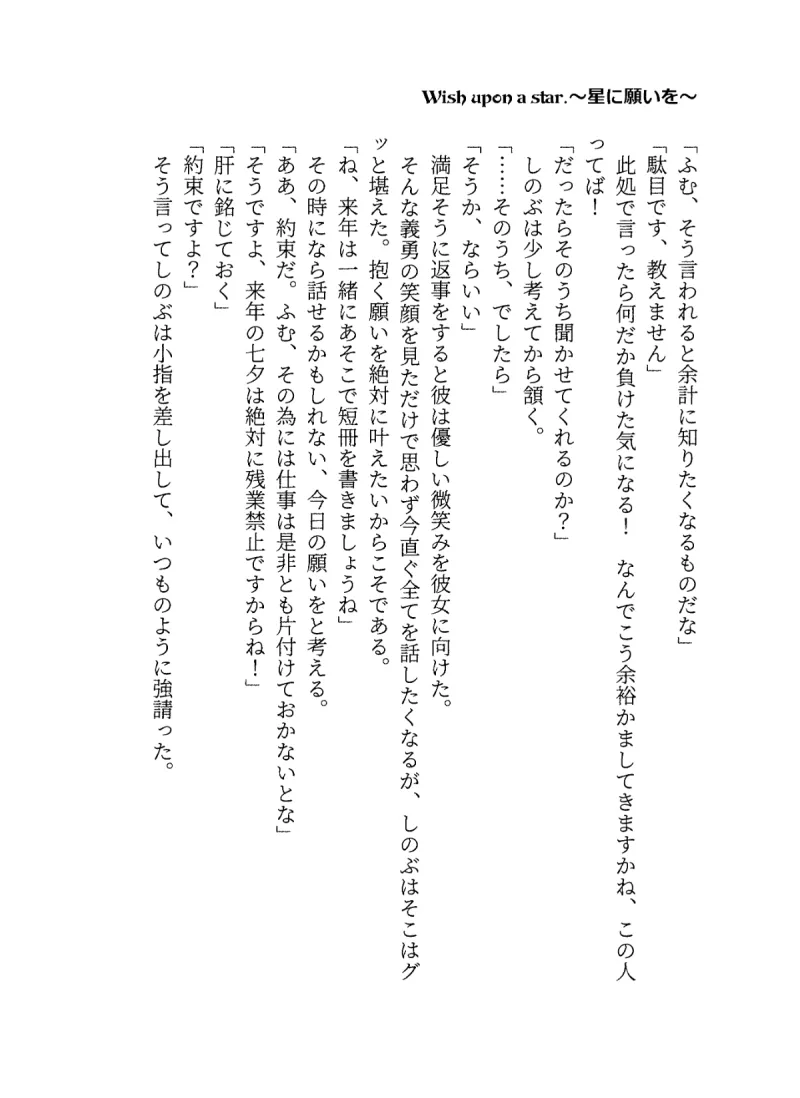
作品紹介
星に願いを
「七夕です、冨◯先生」
「……そうだな」
「七夕デートしたいです、義勇さん」
「……平日だぞ」
「折角の七夕ですよ? デートしたいですっ」
先ほどから続いている押し問答だが、これで何度目だろうかと義勇は思う。
「……胡◯、まだ学校だ」
そして男の言う最後の言葉も決まっていた。
「知ってますよ」
それに不満げに少女が答えるのもまた、である。
今日は義勇の残業があったため二人とも校内にまだいた。既にいつもよりも遅い時間となっているのだが、しのぶも先に帰らずに彼の仕事が終わるのを待っている状態だ。
お陰で大分前から体育準備室で二人きりという状態なのだが、問題有りと思いながら結局はいることを許していた。
「でも折角の二人きりです」
「まあ、確かにそうだが、この格好でいいのか?」
いい加減観念して義勇は尋ねる。何しろ彼の姿は上半身はTシャツ、下半身はトレードマークのジャージ姿なのだ。所謂デートスタイルにはほど遠かった。
「いいですよ。だって可愛い生徒が慕っている先生と学校帰りに偶々会って、序でにちょっと一緒に歩いて帰るだけですから」
そんな偶然が多すぎるとまたカナエに怒られるのだが、それでも義勇には最早断るという選択肢はない。
だからあれこれ片付け、これ以上恋人を待たせないようにとさっさと一区切りを付けて強引に仕事を終わらせた。ああ、そうだ、明日やることが増えようともそれは幸せの代償として甘んじて受けよう。たった今、そう決めた。
「胡◯、帰るぞ」
そう自分の意を伝え、部屋の鍵を持って体育準備室を出る。
「はい、いつでも!」
しのぶは待ってましたとばかりに直ぐさま用意を整え、先に行く義勇を追いかけていく。念のために恋人に忘れ物がないかを確認させてから鍵を閉め、そこを後にした。見回りは終わっているので後は守衛室に鍵を戻すだけだ。
そうして二人が揃って学校の外へ出ると眼前に星空が広がり、どうやら空気が澄んでいるのか星々がかなりはっきり輝いているのが分かった。
「わあ、今日は星が綺麗ですね。七夕にぴったり!」
「ああ、冬ほどでは無いが、綺麗だな」
「んもう! 先生は余計な一言多いですよ。そこは素直に綺麗だけでいいんですからね」
「そ、そうか、すまん」
どうにも情緒というやつは苦手だとは思うが、確かに綺麗なものを綺麗というのは大事なことだろう。ちらりとしのぶへ視線を送る。
「先生?」
大きな瞳で見つめてくる愛らしい恋人に義勇は欣(きん)喜(き)雀(じゃく)躍(やく)な気分になる。勿論、実際に踊り出したりはしないが。
「いや、星空は確かに綺麗だ」
そんな気分であることを隠したくて慌てて義勇はそう言った。どうにもそんな自分が照れくさかったのだ。
「ですよね、ですよね!」
燥(はしゃ)ぐ少女の様子は愛らしいから男はそれを微笑んで見守る。
そのまま取り留めのない雑談をしながら二人で駅を目指して歩いていけば遠くに明るい光が見え、賑やかな音楽が聞こえてきた。
そこは本日、七夕の祭りを行う神社だ。ここら辺では大きな神社であり、少し離れた場所からでも今宵の七夕の祭りへ向かっている人々も見える。
「お祭りですね。楽しそう」
「流石にあちらには行けないぞ。目立ちすぎる」
祭りは当然ながら不特定多数の人間が行く場所であり、誰がいるか分かったものではない。と言うか、通学路上にあるから生徒たちが確実にいるはずだ。実際、祭りの規模もそれなりに大きいこともあり、学内でも噂しているものが多かった。
普通ならば絶好のデートチャンスだからな。
そう思うと我知らずムカついてくるが、それを表に出さぬよう努める。本音を言えば身も蓋もない。
「はあい、分かってます」
しのぶとしては本当なら今直ぐにも一緒に行きたいけれど、義勇の言うとおりなのでそこは抑えるしかなかった。
義勇さんに迷惑かけるのは嫌ですし。
今のこの状況だけでも十分過ぎるはずなのだが、欲望とは果てしない。
「でも来年は一緒に歩いて行けますよね」
義勇をちらりと見遣りながらしのぶは確認するようにそう尋ねた。
「そうだな。それなら問題ないだろう」
しのぶが卒業すれば教師と生徒という柵(しがらみ)が無くなるから二人で行くことに何の障害もなくなる。これはかなり重大かつ重要な変化だ。
「あー、楽しみです」
「ふむ、今のところは……そうだな、遠くからなら」
ふと思い付いた場所があり、義勇は呟くようにそう言った。
あそこなら――しのぶといてもいいだろう。
「遠く?」
不思議な顔をしているしのぶの手を取るとそのまま歩き出す。
「ぎ、義勇さん?」
しのぶの手を握ったまま、義勇がどんどん歩いて行くと高台に小さな公園があり、そこから下で行われている祭りを覗くことが出来た。
義勇がこの場所を知ったのはまだ学園に赴任したばかりの頃である。気が向いて遠回りして帰ったときがあり、その際に見付けたのだ。その時は夕方だったせいもあり、遊ぶ子どもやそれを見守る親などがいたが、今は夜であることも手伝って周囲には二人の他には誰もいない。
「此処からなら目立たないだろう」
「へえ、それも星空とお祭りが見られるからお得ですね」
嬉しそうに微笑う少女を眺め、彼はその目を細めた。
「気に入ってくれたか」
「義勇さんにしては気が利いてますね」
「まだ先生だろう?」
「今は私たちだけだからいいじゃないですか」
「まあな」
そのまま暫く二人で暫く星空と祭りの様子を眺める。
星は彼らの上で満天の空で輝き、地上の方では短冊に願いを書いたのであろう人たちが会場が用意した笹に飾っていく様が見えた。
「ねえ、義勇さん、もしも短冊や星にお願いをするなら何を願いますか?」
今日ならば短冊一択だろうが、今のこの状況では二択になるとしのぶは思う。
「……浮かばん」
俺の願いならもう叶っている。それも叶いすぎるほどに。
けれど本音を言えばもっと望みはある。だが、それは一つではない。
自分でも驚くくらいに貪欲なほどに。そしてそれをただの願い事に対して全て伝えるのは無理と知っている。
だからそう答えた。
「んもう! ロマンチックじゃないですねえ」
「悪かったな。ではお前は何を願うんだ?」
「……」
質問し返されてしのぶは思わず黙ってしまう。言ってもいいのかどうか考えているのだ。
「どうした?」
「こんな時のお願いって口にしたら叶わなくなるって聞いたことがあって……」
「それなら思うだけにするといい」
しのぶの願いであれば是非聞きたいとは思ったが、どんな願望であれ彼女の夢が叶わないというのはもっと見たくはなかった。
「あ~あ、それにしても此処に短冊がないのが残念です」
「なら下に降りるか?」
本来は認めてはいけないことだが、しのぶが望むのならそうしてやりたいと思う。
「いいえ、今日は星に願いますから大丈夫です」
そう言うとしのぶは瞳を静かに閉じた。
義勇さんとずっとずっと一緒にいられますように。
強く強くそう願い、祈る。
その間、義勇はただ静かにしのぶの様子を眺めていた。
ああ、とても綺麗だな、そう思いながら。
暫くしてそっと瞳を開いて義勇の方へと振り向いた。
「もう願ったのか?」
「はい」
「叶うといいな」
「きっと叶うと思います」
「そうか、ならいい」
「ね、やっぱり義勇さんは願わないんですか?」
「既に叶っているし、何かに願う前に自分で叶えたい」
それは本当にそう考えている。何かに頼るのではなく、己の力で叶えたいと。何故なら愛しい者を幸福に出来る喜びを知ってしまったからだ。
「叶っている……ちなみにどんな願いでしたか?」
どきどきしながらしのぶはそう尋ねてみる。もしかしなくても……
「ん? 何だ、そんなことは言わずとも分かりそうだがな」
「――! それって私といるってことですか?」
「ああ、そうだ」
否定する理由など無いからあっさりと肯定するとしのぶは嬉しそうな表情を浮かべた後に神妙な顔つきになった。
「でもそれだと私の方が欲張りなのかも知れないですね」
「成る程、お前の願いは俺に纏わることか」
そして揶揄うように義勇がそう聞くとしのぶはほんの少しだけ頬を膨らませる。どうやら照れているらしい。
「そ、それは内緒です」
「ふむ、そう言われると余計に知りたくなるものだな」
「駄目です、教えません」
此処で言ったら何だか負けた気になる! なんでこう余裕かましてきますかね、この人ってば!
「だったらそのうち聞かせてくれるのか?」
しのぶは少し考えてから頷く。
「……そのうち、でしたら」
「そうか、ならいい」
満足そうに返事をすると彼は優しい微笑みを彼女に向けた。
そんな義勇の笑顔を見ただけで思わず今直ぐ全てを話したくなるが、しのぶはそこはグッと堪えた。抱く願いを絶対に叶えたいからこそである。
「ね、来年は一緒にあそこで短冊を書きましょうね」
その時になら話せるかもしれない、今日の願いをと考える。
「ああ、約束だ。ふむ、その為には仕事は是非とも片付けておかないとな」
「そうですよ、来年の七夕は絶対に残業禁止ですからね!」
「肝に銘じておく」
「約束ですよ?」
「……そうだな」
「七夕デートしたいです、義勇さん」
「……平日だぞ」
「折角の七夕ですよ? デートしたいですっ」
先ほどから続いている押し問答だが、これで何度目だろうかと義勇は思う。
「……胡◯、まだ学校だ」
そして男の言う最後の言葉も決まっていた。
「知ってますよ」
それに不満げに少女が答えるのもまた、である。
今日は義勇の残業があったため二人とも校内にまだいた。既にいつもよりも遅い時間となっているのだが、しのぶも先に帰らずに彼の仕事が終わるのを待っている状態だ。
お陰で大分前から体育準備室で二人きりという状態なのだが、問題有りと思いながら結局はいることを許していた。
「でも折角の二人きりです」
「まあ、確かにそうだが、この格好でいいのか?」
いい加減観念して義勇は尋ねる。何しろ彼の姿は上半身はTシャツ、下半身はトレードマークのジャージ姿なのだ。所謂デートスタイルにはほど遠かった。
「いいですよ。だって可愛い生徒が慕っている先生と学校帰りに偶々会って、序でにちょっと一緒に歩いて帰るだけですから」
そんな偶然が多すぎるとまたカナエに怒られるのだが、それでも義勇には最早断るという選択肢はない。
だからあれこれ片付け、これ以上恋人を待たせないようにとさっさと一区切りを付けて強引に仕事を終わらせた。ああ、そうだ、明日やることが増えようともそれは幸せの代償として甘んじて受けよう。たった今、そう決めた。
「胡◯、帰るぞ」
そう自分の意を伝え、部屋の鍵を持って体育準備室を出る。
「はい、いつでも!」
しのぶは待ってましたとばかりに直ぐさま用意を整え、先に行く義勇を追いかけていく。念のために恋人に忘れ物がないかを確認させてから鍵を閉め、そこを後にした。見回りは終わっているので後は守衛室に鍵を戻すだけだ。
そうして二人が揃って学校の外へ出ると眼前に星空が広がり、どうやら空気が澄んでいるのか星々がかなりはっきり輝いているのが分かった。
「わあ、今日は星が綺麗ですね。七夕にぴったり!」
「ああ、冬ほどでは無いが、綺麗だな」
「んもう! 先生は余計な一言多いですよ。そこは素直に綺麗だけでいいんですからね」
「そ、そうか、すまん」
どうにも情緒というやつは苦手だとは思うが、確かに綺麗なものを綺麗というのは大事なことだろう。ちらりとしのぶへ視線を送る。
「先生?」
大きな瞳で見つめてくる愛らしい恋人に義勇は欣(きん)喜(き)雀(じゃく)躍(やく)な気分になる。勿論、実際に踊り出したりはしないが。
「いや、星空は確かに綺麗だ」
そんな気分であることを隠したくて慌てて義勇はそう言った。どうにもそんな自分が照れくさかったのだ。
「ですよね、ですよね!」
燥(はしゃ)ぐ少女の様子は愛らしいから男はそれを微笑んで見守る。
そのまま取り留めのない雑談をしながら二人で駅を目指して歩いていけば遠くに明るい光が見え、賑やかな音楽が聞こえてきた。
そこは本日、七夕の祭りを行う神社だ。ここら辺では大きな神社であり、少し離れた場所からでも今宵の七夕の祭りへ向かっている人々も見える。
「お祭りですね。楽しそう」
「流石にあちらには行けないぞ。目立ちすぎる」
祭りは当然ながら不特定多数の人間が行く場所であり、誰がいるか分かったものではない。と言うか、通学路上にあるから生徒たちが確実にいるはずだ。実際、祭りの規模もそれなりに大きいこともあり、学内でも噂しているものが多かった。
普通ならば絶好のデートチャンスだからな。
そう思うと我知らずムカついてくるが、それを表に出さぬよう努める。本音を言えば身も蓋もない。
「はあい、分かってます」
しのぶとしては本当なら今直ぐにも一緒に行きたいけれど、義勇の言うとおりなのでそこは抑えるしかなかった。
義勇さんに迷惑かけるのは嫌ですし。
今のこの状況だけでも十分過ぎるはずなのだが、欲望とは果てしない。
「でも来年は一緒に歩いて行けますよね」
義勇をちらりと見遣りながらしのぶは確認するようにそう尋ねた。
「そうだな。それなら問題ないだろう」
しのぶが卒業すれば教師と生徒という柵(しがらみ)が無くなるから二人で行くことに何の障害もなくなる。これはかなり重大かつ重要な変化だ。
「あー、楽しみです」
「ふむ、今のところは……そうだな、遠くからなら」
ふと思い付いた場所があり、義勇は呟くようにそう言った。
あそこなら――しのぶといてもいいだろう。
「遠く?」
不思議な顔をしているしのぶの手を取るとそのまま歩き出す。
「ぎ、義勇さん?」
しのぶの手を握ったまま、義勇がどんどん歩いて行くと高台に小さな公園があり、そこから下で行われている祭りを覗くことが出来た。
義勇がこの場所を知ったのはまだ学園に赴任したばかりの頃である。気が向いて遠回りして帰ったときがあり、その際に見付けたのだ。その時は夕方だったせいもあり、遊ぶ子どもやそれを見守る親などがいたが、今は夜であることも手伝って周囲には二人の他には誰もいない。
「此処からなら目立たないだろう」
「へえ、それも星空とお祭りが見られるからお得ですね」
嬉しそうに微笑う少女を眺め、彼はその目を細めた。
「気に入ってくれたか」
「義勇さんにしては気が利いてますね」
「まだ先生だろう?」
「今は私たちだけだからいいじゃないですか」
「まあな」
そのまま暫く二人で暫く星空と祭りの様子を眺める。
星は彼らの上で満天の空で輝き、地上の方では短冊に願いを書いたのであろう人たちが会場が用意した笹に飾っていく様が見えた。
「ねえ、義勇さん、もしも短冊や星にお願いをするなら何を願いますか?」
今日ならば短冊一択だろうが、今のこの状況では二択になるとしのぶは思う。
「……浮かばん」
俺の願いならもう叶っている。それも叶いすぎるほどに。
けれど本音を言えばもっと望みはある。だが、それは一つではない。
自分でも驚くくらいに貪欲なほどに。そしてそれをただの願い事に対して全て伝えるのは無理と知っている。
だからそう答えた。
「んもう! ロマンチックじゃないですねえ」
「悪かったな。ではお前は何を願うんだ?」
「……」
質問し返されてしのぶは思わず黙ってしまう。言ってもいいのかどうか考えているのだ。
「どうした?」
「こんな時のお願いって口にしたら叶わなくなるって聞いたことがあって……」
「それなら思うだけにするといい」
しのぶの願いであれば是非聞きたいとは思ったが、どんな願望であれ彼女の夢が叶わないというのはもっと見たくはなかった。
「あ~あ、それにしても此処に短冊がないのが残念です」
「なら下に降りるか?」
本来は認めてはいけないことだが、しのぶが望むのならそうしてやりたいと思う。
「いいえ、今日は星に願いますから大丈夫です」
そう言うとしのぶは瞳を静かに閉じた。
義勇さんとずっとずっと一緒にいられますように。
強く強くそう願い、祈る。
その間、義勇はただ静かにしのぶの様子を眺めていた。
ああ、とても綺麗だな、そう思いながら。
暫くしてそっと瞳を開いて義勇の方へと振り向いた。
「もう願ったのか?」
「はい」
「叶うといいな」
「きっと叶うと思います」
「そうか、ならいい」
「ね、やっぱり義勇さんは願わないんですか?」
「既に叶っているし、何かに願う前に自分で叶えたい」
それは本当にそう考えている。何かに頼るのではなく、己の力で叶えたいと。何故なら愛しい者を幸福に出来る喜びを知ってしまったからだ。
「叶っている……ちなみにどんな願いでしたか?」
どきどきしながらしのぶはそう尋ねてみる。もしかしなくても……
「ん? 何だ、そんなことは言わずとも分かりそうだがな」
「――! それって私といるってことですか?」
「ああ、そうだ」
否定する理由など無いからあっさりと肯定するとしのぶは嬉しそうな表情を浮かべた後に神妙な顔つきになった。
「でもそれだと私の方が欲張りなのかも知れないですね」
「成る程、お前の願いは俺に纏わることか」
そして揶揄うように義勇がそう聞くとしのぶはほんの少しだけ頬を膨らませる。どうやら照れているらしい。
「そ、それは内緒です」
「ふむ、そう言われると余計に知りたくなるものだな」
「駄目です、教えません」
此処で言ったら何だか負けた気になる! なんでこう余裕かましてきますかね、この人ってば!
「だったらそのうち聞かせてくれるのか?」
しのぶは少し考えてから頷く。
「……そのうち、でしたら」
「そうか、ならいい」
満足そうに返事をすると彼は優しい微笑みを彼女に向けた。
そんな義勇の笑顔を見ただけで思わず今直ぐ全てを話したくなるが、しのぶはそこはグッと堪えた。抱く願いを絶対に叶えたいからこそである。
「ね、来年は一緒にあそこで短冊を書きましょうね」
その時になら話せるかもしれない、今日の願いをと考える。
「ああ、約束だ。ふむ、その為には仕事は是非とも片付けておかないとな」
「そうですよ、来年の七夕は絶対に残業禁止ですからね!」
「肝に銘じておく」
「約束ですよ?」
そう言ってしのぶは小指を差し出して、いつものように強請った。
「はい、指切り」
「お前は指切り、好きだな」
「だってそうしたら義勇さん、絶対守ってくれますから」
分かった分かったと言い、自分の小指を彼女のものに絡めて指切りをしてやった。
「これで絶対の約束ですよ?」
「ああ、破ったら針千本だな。流石にそんなもの、飲みたくないから守るさ」
そのまましのぶを引き寄せ、抱き締める。
「星、綺麗ですよね」
彼の腕の中が心地よく、そこから覗ける空を見る。先ほどより星たちが綺麗に見えた。
「ああ、でもお前の方が遥かに綺麗だな」
そう義勇が言うと次の瞬間、しのぶの顔が真っ赤に染まって無言になる。
「どうした?」
「義勇さんのくせに! 義勇さんのくせに!」
もう自分でも何を言っているのか分からないが、取り敢えずその言葉を繰り返して彼の胸を軽く叩いた。
「事実だからな。星よりもお前の方が綺麗だと」
愛しい恋人の頭を撫でながら尚も言い続ける義勇に観念するほかないとしのぶは思い、その身を任せる。
綺麗、って言われて嬉しい。そこは素直に喜んだ。
「……本当にそう思ってます?」
「嘘偽りなくそう思ってるな」
「そうですか」
「そうだ」
お互いの顔を見つめながらそう言い合い、やがてどちらからともなく笑い出した。
一通り笑い終えると今度は静かに手を繋ぎ、そのまま互いの指を絡ませていく。それはまるで二人だけの内緒の儀式のよう。
そして――。
そっとキスを交わす――満天の星の下で二人の願いを乗せて。
「はい、指切り」
「お前は指切り、好きだな」
「だってそうしたら義勇さん、絶対守ってくれますから」
分かった分かったと言い、自分の小指を彼女のものに絡めて指切りをしてやった。
「これで絶対の約束ですよ?」
「ああ、破ったら針千本だな。流石にそんなもの、飲みたくないから守るさ」
そのまましのぶを引き寄せ、抱き締める。
「星、綺麗ですよね」
彼の腕の中が心地よく、そこから覗ける空を見る。先ほどより星たちが綺麗に見えた。
「ああ、でもお前の方が遥かに綺麗だな」
そう義勇が言うと次の瞬間、しのぶの顔が真っ赤に染まって無言になる。
「どうした?」
「義勇さんのくせに! 義勇さんのくせに!」
もう自分でも何を言っているのか分からないが、取り敢えずその言葉を繰り返して彼の胸を軽く叩いた。
「事実だからな。星よりもお前の方が綺麗だと」
愛しい恋人の頭を撫でながら尚も言い続ける義勇に観念するほかないとしのぶは思い、その身を任せる。
綺麗、って言われて嬉しい。そこは素直に喜んだ。
「……本当にそう思ってます?」
「嘘偽りなくそう思ってるな」
「そうですか」
「そうだ」
お互いの顔を見つめながらそう言い合い、やがてどちらからともなく笑い出した。
一通り笑い終えると今度は静かに手を繋ぎ、そのまま互いの指を絡ませていく。それはまるで二人だけの内緒の儀式のよう。
そして――。
そっとキスを交わす――満天の星の下で二人の願いを乗せて。
